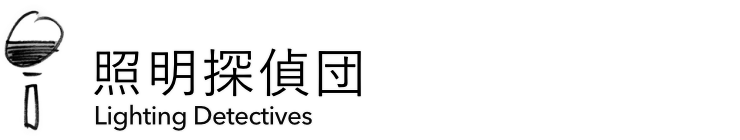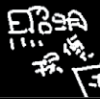2024.11.21-11.22 池田俊一 + 柴田雄太
産業都市として発展してきた四日市。煌びやかな工場夜景と整備が進む市街地の対比が際立つ。産業と生活が共存する都市の照明を調査した。

■四日市について
四日市の歴史は古く、伊勢湾に面した港町として発展し、江戸時代は東海道の宿場町として栄えた。当時、4の付く日に市が開かれたことが市名の由来となっている。戦後は高度経済成長の影響で石油化学コンビナートが建設され、産業の街として発展してきた。石油化学コンビナートから排出された大気汚染物質は、四日市ぜんそくと呼ばれる公害を引き起こしたが、現在の四日市は快適な環境を取り戻しており、工場地帯のすぐそばに住宅街や商店街、人々の暮らしが広がっている。

眺める工場

煙突が頭を覗かせる

第3 コンビナート


住宅街のすぐそばにコンビナート広がる
■3D工場夜景
産業都市として発展してきた歴史を持つ四日市は、2000年代前半の工場夜景ブームと共に注目されるようになった。南北に約10km広がる四日市コンビナートの壮大な工場夜景は、日本5大工場夜景に数えられる。特徴として「空・陸・海」の様々な角度から見られることから3D夜景と呼ばれ、特に工場夜景の映え写真が高い注目を集める。私たちは照明探偵団の視点から、産業都市における四日市の工場夜景の調査を実施した。
■工場夜景の照明器具
巷には建物全体や街全体を映した工場夜景写真が多く、工場で使用されている照明器具を近くから観察する機会はなかなか少ない。オレンジ色のナトリウムランプが使用されているイメージがあったが、実際に観察してみると、白色のLED光源や蛍光ランプが多く使用されていて、配光制御が施された照明器具はなかった。おそらく安全性と作業効率性が優先されているからであろう。グレアや光害に対する配慮はないため、近くで見るととても眩しく感じた。
■「非日常」が日常の工場夜景
いたる所に取付けられた照明が工場を無骨に照らし、工場の特徴的な形状が強調され、工場ひとつひとつの個性が表れていた。写真ではどれも幻想的な世界観を作り出しているように見える。しかし、実際にみた夜景は、写真通りの圧巻の工場夜景もあれば、映え写真として部分的に切り取られた工場夜景もあった。
工場夜景は「幻想的」「非日常」といった普段の生活では味わえない特別な感覚を表す言葉で表現されることがよくあるが、体感として周りの景観に溶け込んだ日常風景の一部のように感じた。

6 つ並んだ冷却塔が特徴的

スポットライトで照らされる

工場夜景ファサードを演出
■工場夜景を観に行こう!
インターネットやSNS上には工場夜景の映え写真が沢山あるが、実際に足を運んでみないと気づけない魅力を見つけることができた。そのひとつが、2018年に開通した産業道路「いなばポートライン」。迫力あるSカーブの道路と海に映り込む工場夜景はまさに映えだが、柱を囲むように配置された赤・黄・緑色に点滅するインジケーターの動きが可愛らしく、写真だけでは伝わらない細やかな魅力があった。
■煌びやかな俯瞰夜景
四日市港ポートビルと垂坂公園展望台の高所から視察を行った。
四日市港ポートビルの展望台は高さ約100m、夜景撮影のための映り込み防止用黒布を貸出していたり、閉館時間午後9時の10分前からライトダウンを行っていたり、夜景鑑賞に特化している。俯瞰夜景であれば奥に向かって徐々に光量が落ち着いていくのが普通だが、約10kmに及ぶコンビナートを見渡せる四日市の工場夜景は、光が途切れることなく奥の奥まで続く。配光制御が施されていない全方向に光を放つ照明器具は、グレアや光害の原因となる。しかし皮肉なことに、高所から見る夜景においては、このような快適とは言えない照明がむしろ綺麗な夜景を創出し、人々を魅了しているように思えた。
垂坂公園にある展望台からは、海に隣接する四日市コンビナートと内陸に位置する市街地を同時に見ることができた。肉眼では写真ほどは鮮明に見えなかったが、コンビナートと市街地の明るさの違いは一目瞭然で、工場の照明がいかに強烈であるかがよくわかる。四日市の俯瞰夜景は、コンビナートと市街地を分断する光と影の水平線が最も印象的だった。

■市街地の光環境
近鉄四日市駅を中心とする市街地を訪れた。駅前の再開発が行われ、中央通りではバスターミナルや円形歩道橋の整備が行われていた。
駅を西側へ抜けると、連続性のある街路灯が2列、それぞれ車道と歩道に立ち並ぶ。色温度は3000Kで統一され、空間全体に一体感がある景観を作り出していた。照明が計画的に整備されており、交通量の多い駅周辺に対して比較的落ち着きのある光環境であったこと、それでいて車道に必要な照度をしっかりと確保していたことが少し驚きだった。
近未来的な形をした道路照明の上部には、インジケーターのような光りが見え、東側から見ると緑色、西側から見ると紫色に光っていた。インジケーターを取付けた意図は分からず、交通信号と見間違えないか少し不安に思う。
駅の東側は、まだ開発途中の様子。整備されていた西側に比べると、少し粗が目立つ。片方が不点灯のブラケット照明、色温度がちぐはぐな街路灯、シェードが割れた街路灯など、これからの改善に期待したい。
■四日市一番街商店街
市街地で最も賑わいのある四日市一番街商店街を歩く。昼間に初めて訪れたメイン通りは、ひと気がなく、アーケードの屋根から落ちる柔らかい自然光とだだっ広く誰もいない空間が、どこか不釣り合いな落ち着きと不気味さを感じさせていたが、辺りが暗くなってからその通りに戻ると、まるでテーマパークのような華やかさに変わっていた。通りの奥には、上からカラーライティング用の投光器、天井を照らすスポットライト、路面を照らすスポットライト、ブラケット照明を設える盛り沢山なアーケード柱を発見。クリスマス間近の街を色どり、人々が行き交う光景がとても愉快であった。隣接する諏訪公園ではイルミネーションイベントが行われていた。拙く、要所要所でありながらも、照明が賑わいを引き出していた。(柴田雄太)



■調査を終えて
工場地帯から放出されるエネルギーの具現化であり、無数の光、ガス焼却の炎、蒸気などが独特の景観を創り出す、それが工場夜景である。光害の代表とも言える工場の夜の姿が、なぜノスタルジックでロマンチックな雰囲気を醸し出すのだろうか。その原因を探求しようと考えたが、気づいたら夜景写真撮影に没頭していた。「美しいものに理由は要らない」という言葉があるが、SF映画のような非日常的な光景に、人は感情的に魅了されるのだろう。
ふと市街地から工場地帯の空を見上げると、雲がじわりと赤く染まっていた。地元の人々にとっては日常的な景色だろうが、私にとっては今回の四日市調査で最も印象深い瞬間だった。それは、怪奇的でありながら、どこか哀愁も感じさせる、非日常が日常に溶け込んだ光景であった。(池田俊一)